個人再生の流れとかかる期間・申立てに必要な書類について解説
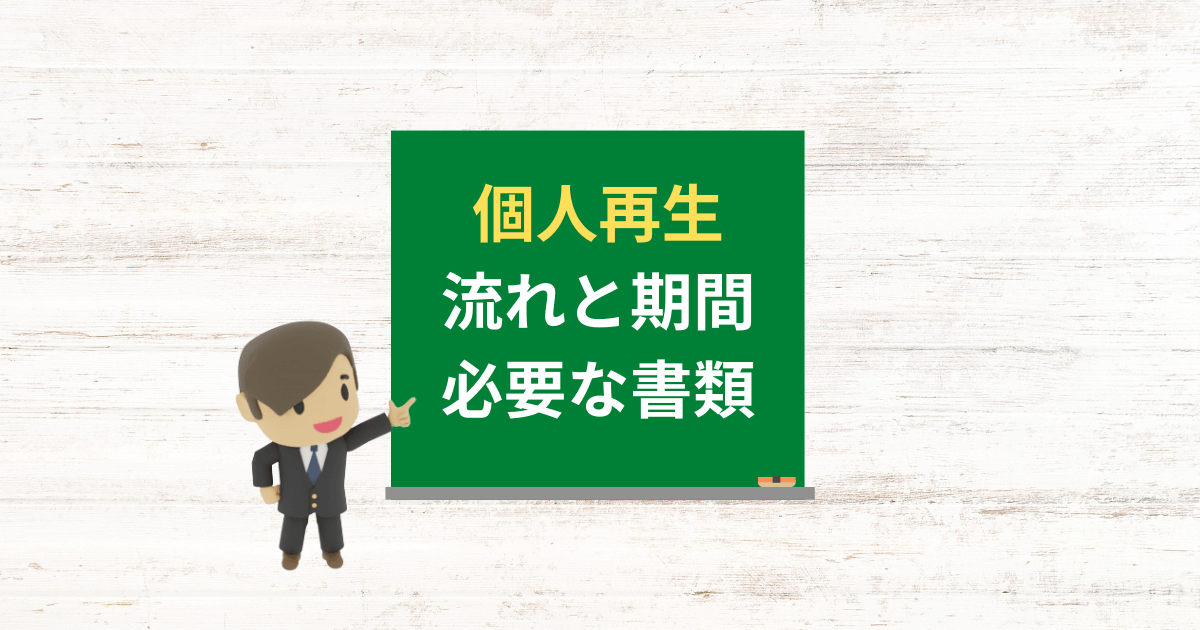
個人再生は、債務整理の一種であり、個人の借金を整理して返済能力を取り戻すための手段です。
ただし、個人再生の手続きに必要な書類を用意して、裁判所に申立をおこない、債権調査を経て再生計画案を提出する必要があります。再生計画案が認められない場合は、手続きすることができません。
この記事では、個人再生の手続きの流れや手続きにかかる期間と注意すべき点を解説します。
| 個人再生の手続きを知る | |
|---|---|
| 個人再生の仕組み | 手続きにかかる費用 |
| デメリットとメリット | 手続きの流れ |
| 小規模個人再生 | 給与所得等再生 |
個人再生の手続きの流れ

弁護士や司法書士に個人再生の依頼を正式に出すと受任通知を各債権者(貸金業者)に通達してくれます。受任通知を受けた業者は取り立てや督促を債務者(あなた)にすることができなくなり、弁護士や司法書士に連絡しなくてはいけません。

財産の把握と書類の準備が整ったらいよいよ裁判所への申立てです。裁判所の申立てには申立書、陳述書、債権者一覧表、添付書類(源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票など)を提出します。弁護士に依頼している場合は自分が裁判所に行くことはありません。
個人再生をおこなう場合は、最初に司法書士・弁護士に相談して、必要な書類を裁判所に提出することが必要です。裁判所から認められれば借金の減額が確定するので、再生計画にもとづいて返済を開始します。
司法書士・弁護士に個人再生相談・契約締結
個人再生は、個人で申し立てることもできますが、実際にはほとんどの人が司法書士や弁護士にサポートを受けています。
司法書士や弁護士に相談すると、借金の総額や所有している財産、収入の状況を聞かれ、個人再生が本当に自分にあっているかどうかアドバイスをもらえます。
もし、個人再生をすることになった場合は、司法書士や弁護士と個人再生委任契約を結び、手続きを進めます。
受任通知と過払い金の計算
司法書士や弁護士と正式な契約を結ぶと、司法書士や弁護士は債権者(金融業者)に「受任通知」を送り、取引履歴の開示を求めます。受任通知を受けた業者は取り立てや督促を債務者(あなた)にすることができなくなり、弁護士や司法書士に連絡しなくてはいけません。
取引履歴を求めたあとは過払い金がいくら発生しているのかを確認します。過払い金が発生していることが分かったら、財産目録に過払い金証明書として裁判所に提出します。
個人再生申立書類の準備

弁護士や認定司法書士は、個人再生の申し立てをするにあたって、収入や家計、財産、資産の状況について詳しく調査します。
調査結果から「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のどちらが適しているかを判断して、裁判所に提出が必要な書類を作成します。
収支・家計の調査
個人再生をおこなうには、給与明細書や源泉徴収票といった収入の証明書類が必要で、2か月分の家計収支表も作成する必要があります。
家計収支表を作成することで、個人再生後の返済ができるかどうかも判断することができます。
債権(財産)の調査
個人再生には「財産の額以上は返済しなければならない」という清算価値保障の原則があり、そのためには財産の調査が必要になります。
そのため、個人再生をおこなうときは裁判所に財産に関する資料「財産目録」提出する必要があります。財産目録には12種類以上の書類があり、細かく記録して提出する必要があります。
財産の申告漏れがあると、財産を隠していると思われて個人再生ができなくなる可能性もあります。また、直前で財産を処分したり贈与したりしても否認の対象になるため意味がありません。
財産目録に関連する書類一覧
財産目録に関連する書類の中で関係のない物は用意しなくて問題ありません。
- 預金通帳の写し
- 未成年の子供名義の預金通帳の写し
- 過払い金の証明書の写し
- 貸付金の証明書の写し
- 売掛金の証明書の写し
- 積立金の証明書の写し
- 退職金もしくは見込み額証明書の写し
- 保険金の証明書の写し
- 保険解約返戻金の証明書の写し
- 有価証券に関する書類の写し
- 車検証の写し
- 車の査定書(2社以上)の写し
- 時価20万円以上の品物の査定書の写し
- 不動産登記事項証明書の原本
- 不動産の査定書(2社以上)の写し
- 固定資産評価証明書の原本
- 賃貸借契約書・住宅仕様許可書の写し
- 相続に関係する書類の写し
- 偏頗(へんぱ)弁済に関する書類の写し
個人再生の手続の選択
個人再生には、一般的な方法である小規模個人再生と、サラリーマンや公務員といった安定した収入を持つ人が利用できる給与所得者等再生の2つがあります。
多くの場合で、小規模個人再生が選択されます。
裁判所に個人再生を申立て
個人再生を申し立てるためには、裁判所に必要な書類を集めて提出しなければなりません。裁判所に書類を提出するときには、印紙代や郵便切手、公告費用などの費用がかかります。
書類に不備がなければ、申し立てをしてから1か月後を目安に個人再生の手続きが始まります。
裁判所の申立てにかかる費用
| 項目 | 手続き費用の内訳 |
|---|---|
| 申立て手数料 (収入印紙代) | 1万円 |
| 郵便切手 | 1,210円~ |
| 官報公告費 | 1万3,000円程度 |
| 予納金(弁護士申立時)※1 | 12,268円 |
| 予納金(本人申立時)※2 | 19万2,268円 |
個人再生員を選任する場合は予納金※2の料金が発生します。
個人再生委員の選出
個人再生を申し立てると、裁判所によって申立て当日〜1週間程度の間に「個人再生委員」が選出されます。
個人再生委員が選出されたら、債務者は個人再生委員との面談が必要になります。また、個人再生委員に対して予納金を支払うことが必要になります。
再生手続きの開始決定
個人再生委員は、面談を通じて借金の理由や負債の状況、履行テストで返済能力を調べ、その結果を元に意見書を裁判所に提出します。
この意見書は、個人再生手続きを進めるべきかどうかがかかれており、裁判官は意見書を参考にして個人再生手続きの開始を決定します。
個人再生委員による意見書に問題がなければ、およそ1か月後に個人再生の手続きを開始する決定を下します。
債権認否一覧表の提出
個人再生が開始されたら、裁判所は各金融業者に「再生手続きの開始決定書」と「債権届出書」を送ります。
債権届出書は、借金の金額を調べるための書類で、各金融業者は開始決定から6週間以内に債権届出書を裁判所に提出します。
そして、申立人(代理人)は、債権届出書に対して金額を承認するかどうかを示す「債権認否一覧表」を裁判所に提出します。もし、申立人が債権届出書に異議をとなえた場合、各金融業者は裁判所に「再生債権の評価の申立て」をすることができます。
最終的に、債権者と債務者の両方が金額に異議をとなえた場合、裁判所が調査を行います。この調査は個人再生委員がおこなって、裁判所は個人再生委員の意見をもとに再生債権の評価を決定します。
裁判所に再生計画案を提出
個人再生が承認された場合、申立人は確定日から2か月以内に再生計画案を作成し、提出する必要があります。再生計画案は、借金をどのように返済するのかを計画することです。
履行テストの開始
再生計画を実行するために、裁判所は予行演習として「履行テスト」をおこなうことがあります。
履行テストは、個人再生が適用された人が再生計画に従って借金を返済できるかどうかを確認するために、一定期間、定められた金額を支払うテストです。
東京地方裁判所などでは、履行テストが実施されることがあります。もし、履行テスト期間中に返済が滞っていた場合は、再生計画どおりの返済が難しいと判断され、個人再生が認められなくなります。
履行テストで支払ったお金は、個人再生委員の報酬を差し引いた後、本人に返還されます。返還されたお金は借金の返済にあてるのが通例です。
書面による決議
小規模個人再生の場合は、申立人が作成した再生計画案に問題がなければ、裁判所は各債権者に計画案を送って書面で意見を聞きます。そして、債権者の多数の意見が賛成なら、個人再生が認められますが、債権者の過半数または債権総額の2分の1を超える不同意があると個人再生ができません。
個人事業主以外で職についてる人で小規模個人再生で失敗した人は、給与所得者等再生を選ぶことになります。給与所得等再生の場合は、最低返済額が小規模個人再生よりも高くなりますが、書面決議はおこなわれないため、借金の減額はしやすくなります。
裁判所が再生計画案の認可・不認可を決定
個人再生の手続きが完了して、申立からおよそ5ヶ月後に裁判所が再生計画案で借金の返済が可能かどうかを判断します。
再生計画が認可されれば、債務者は計画通りに返済することになります。 認可(不認可)の結果は官報に掲載されて、そのおよそ2週間後に認可決定が確定します。
再生計画に沿った返済の開始
再生計画が認可されると、申立人は計画に沿って返済する必要があります。
通常は、減額された借金を3年以内に完済する必要がありますが、3年で完済できない事情がある場合には5年まで延長することができることもあります。
個人再生にかかる期間
個人再生には多数の書類が必要であるのでそれらを集めるだけでも時間がかかります。
また手続き中にさまざまな手順があるので、最短でも数ヶ月以上の時間が必要になります。
個人再生の申立てから再生計画案の認可までの期間
個人再生手続きの開始決定は、個人再生委員が選任される場合には、申立から約1ヶ月後になります。選任されない場合は、申立から1週間以内に決定が下りることもあります。
再生計画案を提出する時期は開始決定からおよそ3~4ヶ月後となり、再生計画認可決定は提出から1~2ヶ月後になることが多いです。
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 個人再生手続開始決定 | 申立ての約1ヶ月後 |
| 再生計画案提出 | 個人再生手続き開始決定の3~4ヶ月後 |
| 再生計画案の認可(不認可)決定 | 再生計画案提出から1~2ヶ月後 |
一般的に、申立から認可決定までにはおよそ6ヶ月程度かかりますが、事案の内容や裁判所によって期間は違う場合があります。
個人再生の手続き後の返済期間
再生計画に基づいた返済期間は原則3年ですが、特別な理由があれば最大5年に延長することができます。
特別な理由とは、教育費や医療費の負担が大きい場合や収入の減少があった場合、あるいは債務額が高額で3年では払えない場合などが含まれます。
個人再生後の影響がある期間
個人再生をすると信用情報に事故情報として登録されるので、10年間ほどブラックリスト状態になります。
ブラックリストに載ると、ローンやクレジットカードの申し込み、スマートフォン端末の分割払いなどができなくなります。
個人再生手続きの必要書類
個人再生の申立には、申立書や債権者一覧表、住民票のコピー、財産目録などの書類を裁判所に提出する必要があります。
作成が必要な書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 家計収支表
- 財産目録
個人再生申請に必要な書類には、申立書や債権者一覧表、財産目録などがあります。
これらは、司法書士や弁護士に依頼して作成してもらうことができます。
また、陳述書や家計収支表は本人が下書きを作成して、司法書士や弁護士に清書を依頼するのが一般的です。
収集しておく書類
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 確定申告書
- 住民票
- 預金通帳や取引履歴
- 車検証と査定書
- 保険証書と解約返戻金証明書
- 不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書
- 住宅ローン契約書や保証委託契約書
司法書士や弁護士の指示に従って、必要な書類を集めることが重要です。
個人再生の流れに関するよくある質問
- 個人再生の期間はどのくらい?
-
個人再生の申し立てから個人再生手続きの開始決定まで1か月程度、その後3~4か月で再生計画案を提出、提出後1~2か月で再生計画案の認可(不認可)決定がなされます。申し立てから決定まで半年以上はかかります。詳しくは「個人再生にかかる期間」をご確認ください。
- 個人再生に必要な書類は?
-
個人再生の申立には、申立書や債権者一覧表、住民票のコピー、財産目録などの書類を裁判所に提出する必要があります。詳しくは「個人再生手続きの必要書類」をご確認ください。


