任意整理の費用を払えない人がみんなやってる安くする方法

任意整理は着手金、基本料、成功報酬の3項目からお金を取られるため借金を解決するのに5万円~15万円かかります。
任意整理の費用を払えず借金の整理をしたくでもできない人が多くいるため、設けられた救済処置があります。
しかし、司法書士や弁護士は自分たちの売上が下がるので費用を安くできることを教えてないことがほとんどです。
任意整理の費用が払えない人がみんなやっている安くする方法を知れば、毎月の負担額を5000円~1万円にして、借金を減らすことができます。
1円でも安く借金問題を解決したい人は必見です。
任意整理にかかる費用の相場
| 費用名目 | 費用の相場 |
| 相談料 | 0円~5,000円 |
| 着手金 | 1社あたり20,000円~50,000円 |
| 基本報酬 | 1社あたり20,000円~50,000円 |
| 減額報酬 | 減額した金額の10% |
弁護士・司法書士に依頼する場合、弁護士や司法書士に相談する時にかかる「相談料」、正式に依頼するときにかかる「着手金」、任意整理の手続きでかかる「基本報酬」、払いすぎている利息を貸金業者から取り戻した金額に応じてかかる「減額報酬」の4つが費用に含まれています。
任意整理を依頼する際にかかる費用相場は1社あたり40,000円~105,000円程度と、事務所によっては多額の費用がかかります。
任意整理の費用をできるだけ安くする方法

原則として任意整理を依頼すると、対象となる借金の返済が一時的にストップします。和解して返済額が決定するまでに時間がかかるため、その間に事務所にかかる費用を支払う流れになります。
また、依頼する弁護士・司法書士事務所や手続きの仕方によっては任意整理にかかる費用を安くすることができます。
費用を分割払いできる事務所に依頼
多くの人が任意整理の費用を支払うのが心配だと思っています。しかし、多くの弁護士や司法書士の事務所は費用を分割して支払うことができるので、負担のないようにお支払いできます。
事務所にかかる費用を支払い終えてから、任意整理した後の借金を返済できるようにスケジュール調整をするので、費用の支払いと借金の返済のタイミングが重なるような心配はありません。
費用を分割して支払う回数は事務所によって違いますが、多くの事務所では6回から12回の分割払いをやっています。
6回払いで費用を支払った場合
4社分の任意整理について、借り入れ、返済、収入、支出といった状況をもとに費用と支払い回数を話し合った結果、120,000円を6回払い(1回あたり20,000円)となりました。費用の支払い日は依頼者の給料日のあとに合わせて日程調整をします。
| 1ヶ月目 | 相談 | 0円 |
| 2ヶ月目 | 受任通知の送付・費用の支払い | 20,000円 |
| 3ヶ月目 | 費用の支払い | 20,000円 |
| 4ヶ月目 | 費用の支払い | 20,000円 |
| 5ヶ月目 | 費用の支払い | 20,000円 |
| 6ヶ月目 | 費用の支払い | 20,000円 |
| 7ヶ月目 | 費用の支払い | 20,000円 |
| 8ヶ月目 | 貸金業者と和解、借金の返済開始 | 和解して確定した返済額 |
費用を後払いができる事務所に依頼
司法書士や弁護士の多くは、お客様が委任契約をする時に必要な費用や書類作成、貸金業者との交渉の費用を先に支払ってから、貸金業者との交渉を始めます。しかし、一部の事務所では、書類作成や交渉の費用を、貸金業者と和解した後に解決報酬金として後払いできることもあります。
後払いになるため任意整理の手続き中の支出を抑えることができますが、任意整理の手続きが完了した後に必ず支払うことになりますので、費用に充てるお金は確保するようにしましょう。
費用が安い事務所に依頼
日弁連(日本弁護士連合会)や日司連(日本司法書士会連合会)では、任意整理にかかる費用についての指針が定められています。
これらはあくまでも指針であり、定められた指針の範囲外の費用を設定しても問題はないとされています。指針で示された金額よりも高い費用を設定している事務所もあれば、指針で示された金額よりも低い費用を設定している事務所もあります。
任意整理を依頼する前に、事務所が指針よりも安い費用を設定しているか確認するべきです。特に指針より大幅に安い費用を設定している事務所の場合は、貸金業者との交渉経験が豊富なのかを確認することが重要です。
任意整理で借金を減らすためには、交渉力が重要ですが、費用が安くても交渉経験が浅い事務所に依頼すると、借金を減らすことができない場合があります。
日本弁護士連合会の費用指針(任意整理)
| 着手金 | 基本報酬 | 減額報酬 |
| 上限なし | 20,000円以下/1社 | 減額分の10%以下 |
日本司法書士会連合会の費用指針(任意整理)
| 着手金+基本報酬 | 減額報酬 |
| 50,000円以下 | 減額分の10%以下 |
任意整理する貸金業者を選ぶ
任意整理をすることで、ローンを組んでいる貸金業者、使っているクレジットカード会社、保証人や連帯保証人が付いている借金、銀行に開設している口座などを任意整理の対象から外すことができます。
弁護士や司法書士が設定している費用形態によっては、任意整理の対象にする貸金業者の数が増えると、事務所に支払う費用の総額が高くなる可能性があります。
任意整理する貸金業者が多い場合、金利が高くて借金の金額が多い貸金業者だけを任意整理することで、事務所にかかる費用を抑えながら返済額を減らすことができます。
一部の事務所では、任意整理で減らした月々の返済額や手続きする貸金業者の数によって費用を調整できるので、正式に契約をする前に弁護士・司法書士に相談するべきです。
法テラスに相談
法律支援を目的とした国の機関である法テラス(日本司法支援センター)が行っている「民事法律扶助制度」を利用することで、任意整理にかかる支払いを毎月5,000円から10,000円に減らすことができます。
この制度は、司法書士や弁護士に依頼する費用を支払うことができない人が利用できます。ただし、利用するには月給や資産に基準があります。
任意整理して借金を減らすまでの流れ
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、およそ2か月〜4か月で貸金業者と和解することができます。和解するまでの手続きのほとんどは依頼した弁護士・司法書士に任せられます。
任意整理の手続きをした後は、貸金業者と和解した契約に基づいて3年~5年かけて借金を返済することになります。
相談・依頼

債務整理を取り扱っている弁護士や司法書士に相談します。返済状況を説明して、任意整理で借金を返済できることが確認できたら、正式に依頼をします。
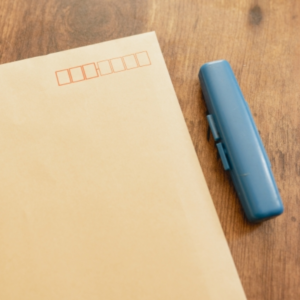
任意整理を依頼したら、弁護士・司法書士が貸金業者に受任通知を送付します。受任通知が貸金業者に届いたら返済の督促が止まりますが、依頼した即日に止まることもあれば、3日で止まることもあります。

弁護士・司法書士が各貸金業者から借りた金額や返済状況を知るために、「取引履歴」の開示を請求します。取引履歴には、いつ、いくら借りたのか、いつ、いくら返済したのかなどの借入状況や返済状況が記録された資料であり、開示請求をしてから1週間から1か月程度で取引履歴を入手することができます。

貸金業者から取引履歴を受け取れたら、過払い金がいくらあったかを計算します。過払いがあった場合は、貸金業者に対して過払い金請求を行います。

残りの借金の返済内容について貸金業者と直接交渉します。交渉した内容について和解ができた場合に和解契約を結びます。交渉から和解までには大体1か月~2か月かかります。

もし貸金業者との交渉で和解に至らなかった場合、裁判になる可能性があります。任意整理における裁判では、裁判上での和解によって解決します。裁判で和解するまでには半年程度の時間がかかることが多いです。

直接交渉で和解あるいは裁判で両者が和解した支払い条件に基づいて返済をしていきます。
任意整理を依頼した後に費用が払えないときの対処法

任意整理を依頼した事務所に相談
任意整理をする場合、予期しない事情で支払いができなくなることがあります。例えば、会社の業績が落ちて収入が落ち込んだり、病気にかかって出費が増えた場合などです。
支払いができなくなると、弁護士や司法書士との契約が解除され、貸金業者から督促状が届く可能性があります。督促状を無視して返済金額を延滞すると、和解契約が無効になり、一括請求を受けるリスクがあります。
費用が払えなくなったり返済ができなくなったりする場合は、なるべく早く弁護士や司法書士にご相談してリスクを最小限に抑えるようにしてください。
2か月分の滞納になる前に支払う
任意整理の期間中に、2か月分の支払いを滞納すると、残りの借り入れを一括で請求されます。ただし、滞納が1か月分の場合は支払いを続けることができます。
そのため、次の月に2か月分の支払いをするか、翌月と翌々月に1.5か月分の支払いをすることで、または1か月遅れの状態を維持し、次のボーナスで遅れ分を支払うことで解決することができます。
払えないからとバックレようとしては絶対にいけません。目の前の借金からは一時的に逃げられますが、返済が遅れたことによる遅延損害金は最大で20%も発生します。
再和解の交渉をする
任意整理の支払い期間中に2か月分の支払いを滞納する場合は、もう一度和解する必要があります。
ただし、再和解の場合は条件が厳しくなってしまい、未払いが1か月あれば一括請求されることがあったり、支払い期間が短くなって毎月の支払額が増えたりする可能性があります。
追加介入をする
任意整理していない借金を任意整理することで毎月の支払額を減らすことができます。
普段使っているクレジットカードや、車や住宅を担保にしている借金、保証人のいる借金など、任意整理をして減らせる借金があるなら追加介入をすることも可能です。
個人再生または自己破産をする
任意整理、再和解、追加介入などを行っても、返済状況が改善しない場合は、個人再生か自己破産を選択することになります。個人再生は最大10%まで減らした借金を3-5年間に分割して返済することができて、自己破産は借金を全て放棄して、借金を0にすることができます。
任意整理の費用についてよくある質問
- 任意整理の費用相場は?
-
任意整理を弁護士や司法書士に依頼する際の費用相場は、1社あたり40,000円~105,000円程度で、事務所によっては多額の費用がかかります。
費用内容の内訳は最初に相談する「相談料」、正式に手続きを開始する「着手金」、任意整理手続きの「基本料金」、貸金業者から回収した利息の額に応じて算出する「減額報酬」の4つの費用です。
各費用の金額の内訳と相場は「任意整理にかかる費用の相場」を確認ください。
- 任意整理後に支払いが遅れたらどうなる?
-
任意整理した後に2回以上支払いが滞ると「期限の利益」を喪失し、一括請求されてしまいます。
翌月に滞り分を支払ったとしても、元の分割払いのプランに戻すことはできず、遅延損害金が残債に加算されます。支払いが遅れた場合の対処方法は「再和解の交渉をする」を参照ください。
